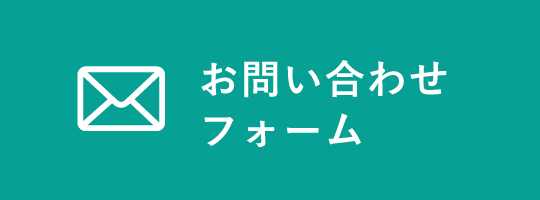養育費は、離婚後の子どもの生活費に関わる問題です。養育費について問題となる点を整理すると以下のとおりです。
1 養育費とは
養育費は、法律上の親は、未成熟子に対して扶養義務(民法877条以下)を負担しているところ、監護親から非監護親に対し、監護費用(民法766条)として請求されるものです。
親権と監護権が分離された場合には、どちらが支払義務を負うのか整理して考える必要があります。
2 養育費の支払義務
養育費の発生時期
養育費の根拠は、親の子に対する扶養義務ですから、子の要扶養状態と親の扶養可能状態があれば、その時点から養育費を請求することは理論上可能です。
もっとも、あまりにも過去に遡って請求すると、義務者にとって酷となることから、ある程度の範囲に限定されることが多いようです。
実務上は、養育費の発生時期については、婚姻費用分担請求と同様、以下のように整理できます。ただし、この分類にあてはまらない裁判例もありますので、あくまでも参考として、個別の事案ごとに検討するようにしましょう。
- 別居時
- 請求時①(調停や審判の申立前に請求していたことが証明できる場合はこの請求時)
- 請求時②(上記証明ができない場合は調停や審判の申立時)
養育費の終期
次に、養育費をいつまで支払うのかという終期の問題があります。実務上、調停等ではおおむね以下の3つのパターンで提案されることが多いといえます。
- 未成熟子が満18歳に達する月まで
- 未成熟子が満20歳(成年)に達する月まで
- 未成熟子が大学等高等教育機関を卒業する月まで(通常22歳まで)
協議や調停でお互いに合意できるのであれば、いずれの終期でも問題はありませんが、当事者間で合意ができない場合、3のように20歳をすぎる終期を求めることができるかどうかという問題があります。
この点、「子が成年に達するまでに限定する」という裁判例(大阪高決昭57・5・14家月35巻10号62頁)もあれば、「大学を卒業する付きまで」とする裁判例(東京家審平18・6・29家月59巻1号103頁)もあるため、どちらか一義的に決まっているということはできません。
したがって、夫婦の最終学歴や収入状況等、具体的な事実を主張・立証して妥当な養育費の終期を求めることになります。
養育費の支払方法
養育費は、月ごとに発生する定期金債権であり、一括払いを請求することは困難です。
もっとも、当事者双方が合意して一括払いをすることは可能ですが、課税上の問題や、一括払いした後、全額使いきったとして再度養育費を請求される可能性もありますので、一括払いをすることでよいかどうかは慎重に検討しましょう。
なお、養育費の一括払いをした後に、再度養育費を請求されたものの、結論として否定された裁判例があります(東京高決平10・4・6家月50巻130号30頁)。
3 婚姻費用・養育費の算定方法
「婚姻費用・養育費算定表」の利用
婚姻費用及び養育費の算定にあたっては、実務上、「簡易迅速な養育費等の算定を目指して−養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(判タ1111号285頁以下。以下、この論文291頁掲載の計算式を「算定方式」、297頁以下の票を「算定表」といいます)によって判断されることが通常です。
算定表の使用にあたっては、権利者と義務者双方の収入を確認することが必要になります。
「婚姻費用・養育費算定表」の限界
この算定表に従って、調停や審判が進められることが通常です。ですが、中には算定表を形式的に利用するとかえって不都合が生じる場合や、算定表に当てはまらない場合があります。
例えば、権利者・義務者の基礎収入が、算定表の上限を超えている場合や、当事者間の子の数が算定表の想定する人数以上の場合、当事者双方にそれぞれ監護する子がいる場合などです。
このように、算定表は決して万能ではなく、個別の事案に応じて修正していく必要があります。